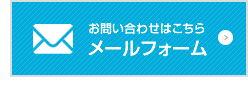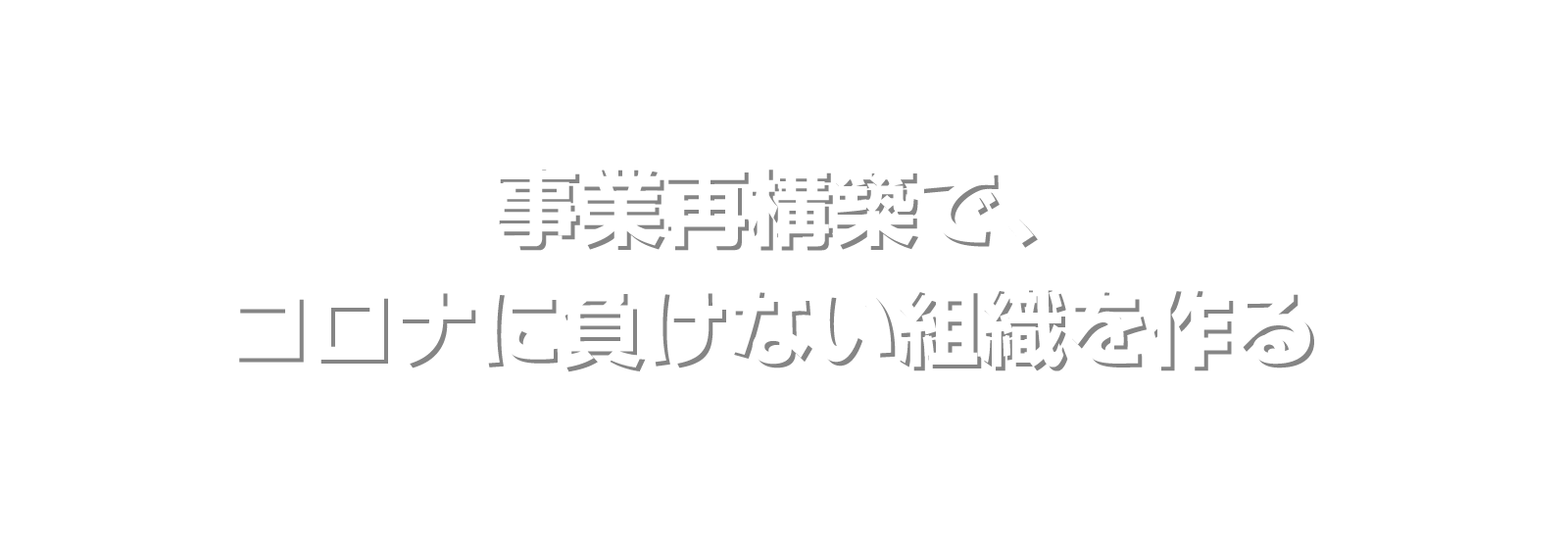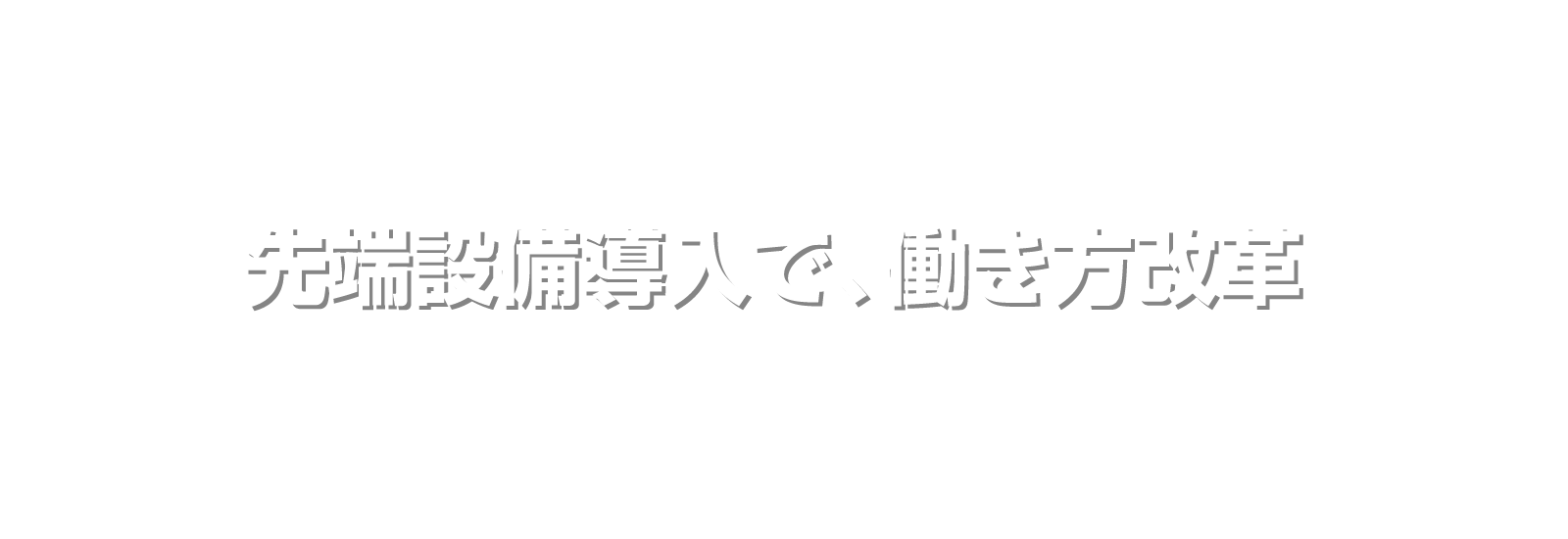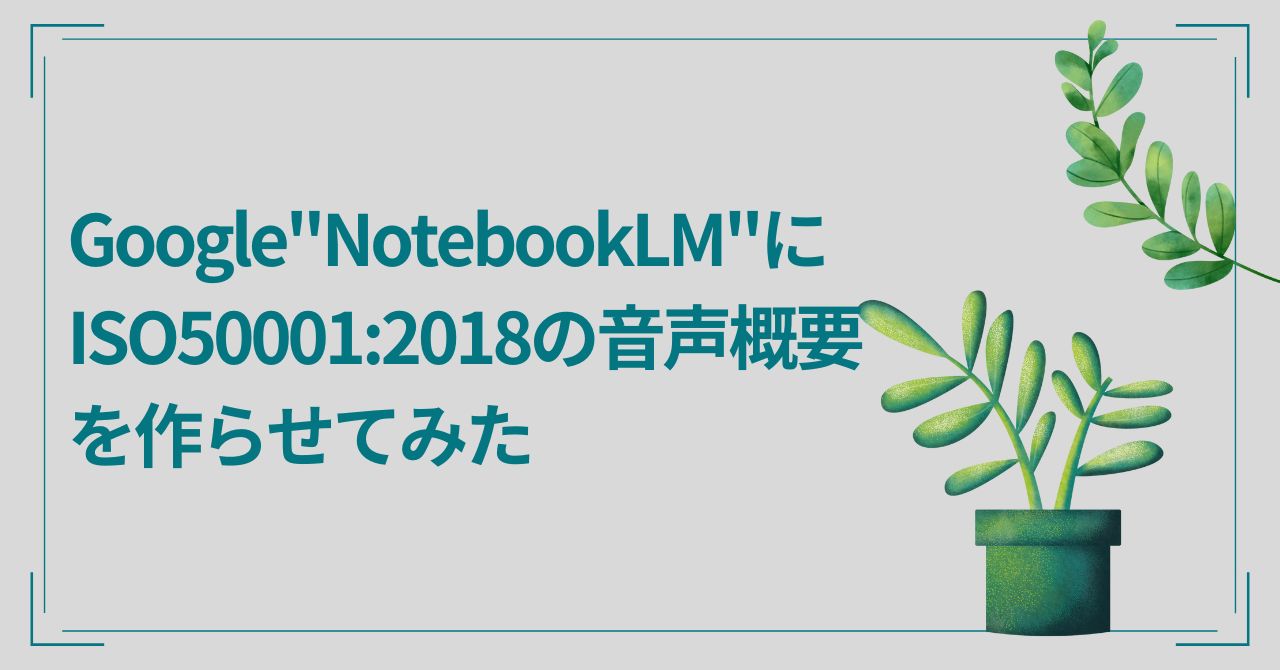おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
Googleの"NotebookLM"ってご存知ですか?簡単に言うと、アップロードした資料をパッと読んで、むずかしいことをかんたんにまとめたり、質問に答えたりしてくれるAIつきのノートなんですが、これを使ってISO50001:2018の概要を、ラジオ風に読み上げてもらいました。
スポンサーリンク
GoogleのAI "NotebookLM"とは
Google NotebookLM は、Google Labs が開発する AI 搭載のリサーチ支援ツールです。
ユーザーが Google ドライブにアップロードした PDF、Google ドキュメント、ウェブページ、Google スライドなどの情報を取り込み、AI(Google Gemini)を使って要約・解説・Q&A を生成するというものです。
主な機能
- 要約と解説:大量の資料からポイントを抽出し、短いテキストでまとめる。
- 質問応答:資料の内容に関する質問に対し、モデルが回答を生成。
- ブレインストーミング:関連トピックのアイデア出し支援。
- 音声概要:資料をポッドキャスト風に読み上げる音声要約機能。50 言語以上に対応
この「音声概要」というのが面白かったので、ちょっと紹介しますね。これは男性と女性が会話をしながら、アップした資料の概要を掛け合いをしながら説明するという機能なのです。ちょうど、ラジオでパーソナリティとゲストが会話しているような感じで、アップした資料を説明してくれるようなイメージです。
ISO5001:2018(エネルギーマネジメントシステムの国際規格)についての資料を読み込ませて、その概要を生成してもらいました。
実際の音声はこちら
実際にNotebook LMが生成した「音声概要」を聴いていただきましょう。
こんな感じで2人の会話形式で概要を説明してくれる
音声概要のイメージを文字起こししてみました。↑の動画を再生できない人は、以下の会話を聴いてイメージを掴んでみてくださいね。
Aさん: こんにちは。今回は ISO 50001:2018 エネルギーマネジメントシステムの国際規格ですね。お預かりした資料をもとに掘り下げていきたいと思います。組織がエネルギーパフォーマンスを体系的に改善していくための枠組みということですよね。
Bさん: はい、そうです。ISO 国際標準化機構が定めたものです。
Aさん: で、この 2018 年版というのは、2011 年の旧版から改訂されていて、改訂版なんですね。
Bさん: その通りです。大きな変更点としては、ハイレベルストラクチャーが採用されたことです。
Aさん: ハイレベルストラクチャーとは、他の ISO 規格、例えば品質マネジメントシステムの ISO 9001 や環境マネジメントシステムの ISO 14001 と同じ構造になったということですか?
Bさん: はい。複数のマネジメントシステムを持つ組織にとっては、統合しやすくなりました。
Aさん: なるほど。運用が楽になるわけですね。
Bさん: ええ。そしてもう一つ大きいのが、トップマネジメント、つまり経営層の役割や関与がより強く求められるようになった点です。
Aさん: 具体的に、この ISO 50001 の狙いはどこにあるのでしょうか?
Bさん: 組織がエネルギーパフォーマンス(エネルギー使用量や消費量を総合した指標)を継続的に改善していくためのシステムやプロセスを構築し、確実に運用できるようにすることです。
Aさん: 継続的改善ですか?
Bさん: はい。「継続的」というのがポイントで、組織によっては文化的な変革を伴うことが多いのです。
Aさん: 文化的な変革というと?
Bさん: 省エネ活動が特別なものではなく、日々の業務の中に当たり前に組み込まれるような意識の変化を指します。
Aさん: だからこそ、トップのコミットメントが重要になるわけですね。
Bさん: その継続的改善の仕組みとして、PDCA サイクルを使います。
Aさん: PDCA とは何ですか?
Bさん: Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のことで、計画し、実行し、評価し、改善します。Plan の段階ではまずエネルギーレビューを行い、どこでどれくらいエネルギーを使っているかを分析します。
Aさん: そこからリスクや機会を考え、具体的な行動計画を立てるわけですね。
Bさん: その通りです。Do の段階で計画を実行し、設計や調達の段階からエネルギーパフォーマンスを考慮するのも重要です。
Aさん: 上流から考えないとあとでできることが限られますね。
Bさん: そして Check の段階で、計画通りに進んでいるか、パフォーマンスが向上しているかをデータで確認します。そのために「エネルギーパフォーマンス指標」と「エネルギーベースライン」が必要です。
Aさん: 指標と基準値ですね。
Bさん: はい。さらに 2018 年版からは「データの正規化」の考え方も導入されました。
Aさん: 正規化とは?
Bさん: 例えば生産量が増えればエネルギー消費も増えますが、外部要因の影響を取り除いて純粋な改善度合いを比較できるようにすることです。
Aさん: 条件を揃えて比較可能にするということですね。
Bさん: そうです。そして Act の段階で、計画通りでなかったりさらに改善できる点があれば是正措置を講じて次の計画に反映します。このサイクルを繰り返していきます。
Aさん: 非常に合理的ですね。
Bさん: 導入メリットとしては、体系的にエネルギー管理ができるためコスト削減につながりやすいことがまず挙げられます。
Aさん: それは大きいですね。
Bさん: さらに競争力の向上や、エネルギー消費が減れば温室効果ガス排出も減るので、環境面での貢献も期待できます。
Aさん: 気候変動の目標達成にも役立ちますね。
Bさん: ビジネスプロセスに組み込めば相乗効果も生まれます。この規格は大規模工場だけでなく、中小企業でも適用可能で、組織の状況やリソースに応じてシステムの複雑さを調整できます。
Aさん: 単独運用も、ISO 9001 や ISO 14001 など他のシステムと統合しての運用も可能というわけですね。柔軟性が高い。
Bさん: ええ。重要なのは、エネルギー効率の数値目標ではなく、継続的に改善するプロセスをデータで示すことです。
Aさん: 達成度よりプロセスと改善の証明が重要ということですね。
Bさん: まとめると、ISO 50001 は PDCA サイクルをベースにデータを活用し、エネルギーパフォーマンスを継続的に改善する仕組みであり、トップ経営層の関与が不可欠です。
Aさん: どんな組織でも状況に合わせて使え、改善プロセスそのものを重視している点がポイントですね。
Bさん: 最後に、資料にあった「文化的な変革」という言葉が気になりました。
Aさん: はい。
Bさん: エネルギー管理がコスト削減や義務を超えて組織文化として根付いたとき、働く人の意識や日々の行動は具体的にどう変わるのでしょうか。
Aさん: 全員が自然に「もっと効率よくできないか」と考えるようになる組織になるかもしれませんね。
Bさん: そんな視点で考えてみるのも興味深いです。
Aさん: 今回の探究はこの辺までとしましょうか。
Bさん: そうですね。
ゆっくり解説みたいなものを自動で生成してくれるようなサービスですよね。資料の概要を掴む程度であれば、これでじゅうぶんな気もしますね