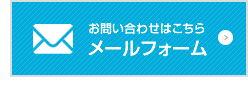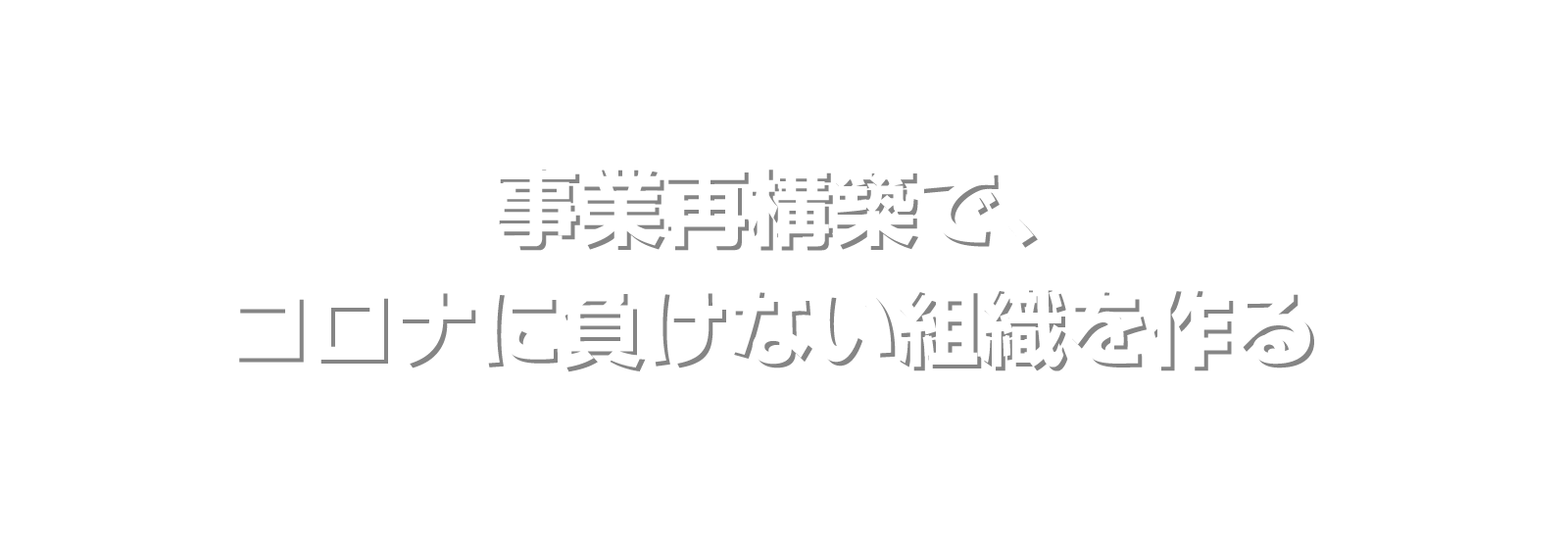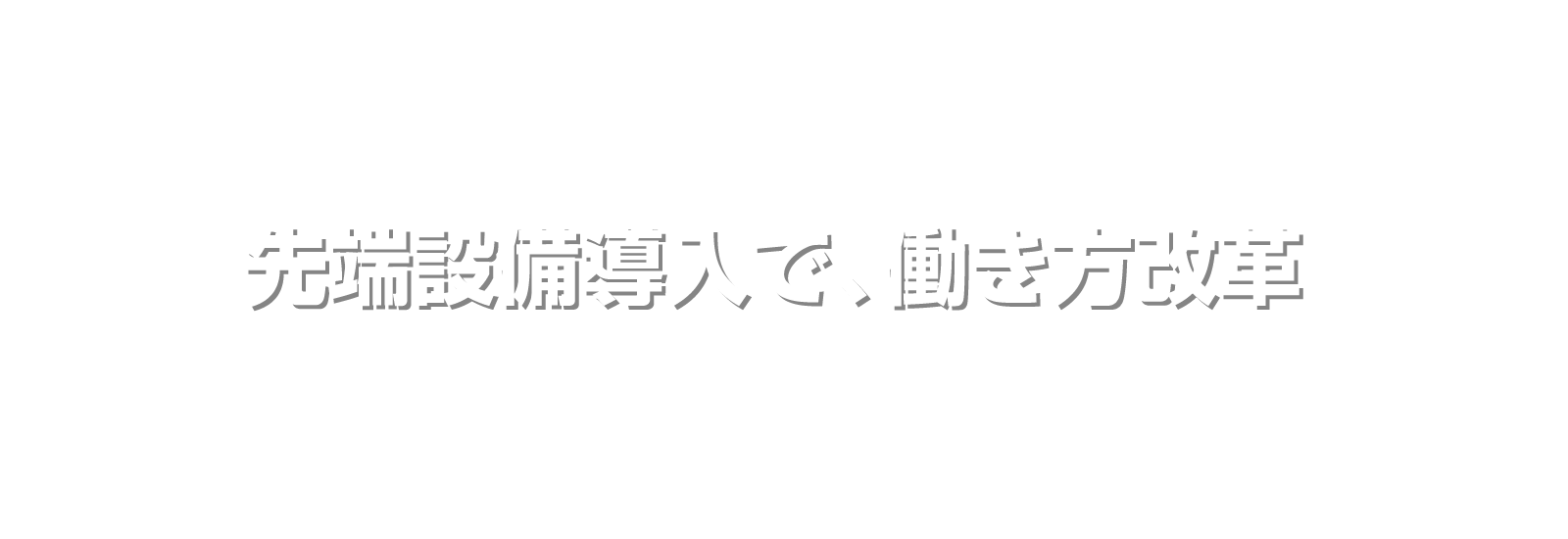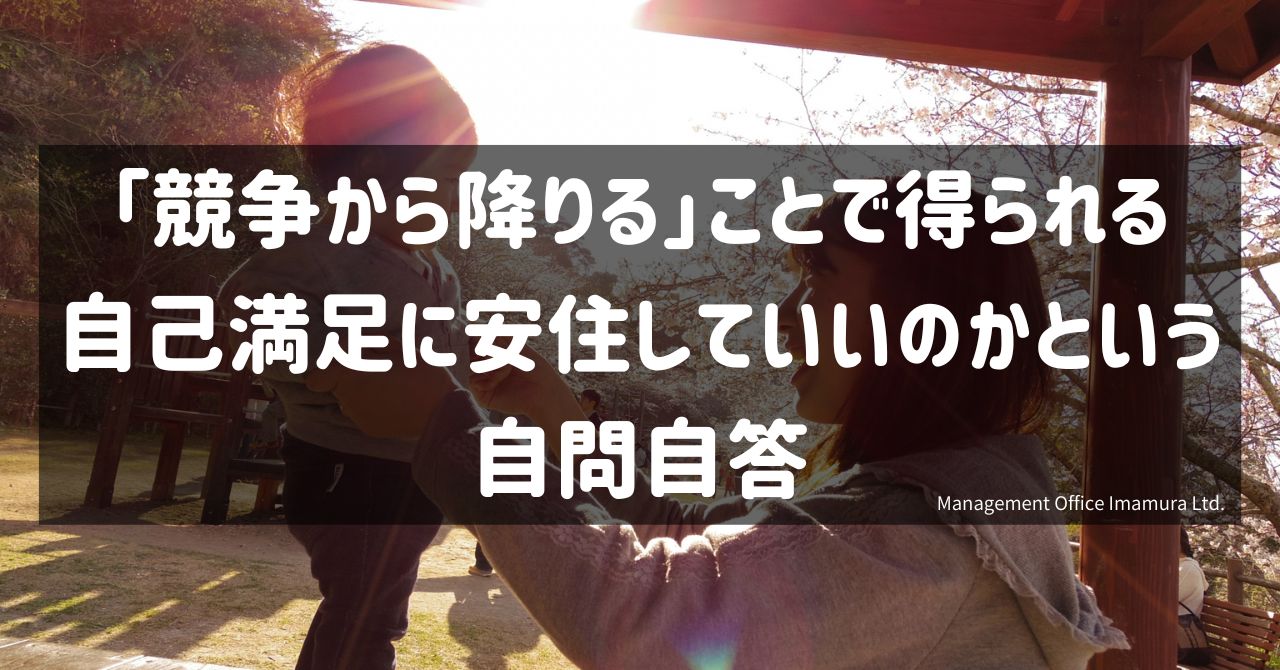おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
週末のエモブロです。ぼくはいろいろあって、もう「競争から降りよう」と決意したダメ人間です。「競争から降りる」と決めることはすごく気持ちいいんですよね。でもその気持ちに安住していいのか?という葛藤もあったりします。
スポンサーリンク
「競争から降りよう」という気持ち
ぼくは10年くらい前から「競争から降りよう」という気持ちが強まっています。というのも、それまでのぼくの人生はずっと「競争に勝ち残ろう」という方針だったのですが、10年くらい前にウツになってしまったからですね。
その時にいろいろ考えて「競争に食らいついて、勝ち残ろう」とする考え方がそもそも間違っているんじゃないかと思ったんですよね。というのも、それまでの人生、受験や就活、資格取得、会社内での競争などに真正面から向き合って、それなりに競争に勝ち残ってきたはずなんですけど、自分自身はちっとも幸せにならなかったどころか、うつ病にまでなってしまったんですよ。
だから競争から降りて、競争から距離を置くことが、実は自分の幸せにつながるんじゃないかと思ったんですよね。
「競争」を否定したい気持ちは、ぼくらの世代には共通した価値観でもある
ここからはぼくの勝手な思い込みになりますけど、「競争に食らいついて、勝ち残らなければ価値がない」という考え方と同じくらい、僕らの世代には「競争を否定したい」という気持ちがあるんじゃないかと思うんですよね。
ちょっと話は飛躍しますが、90年代には「ゆとり教育」がクローズアップされました。受験競争によって子どもたちは疲弊しており、校内暴力、いじめ、不登校などの原因になっているので、学習負担を減らすべきだという考えから生まれた「ゆとり教育」ですが、実は日本の教育は1977年改訂学習指導要領から、過度な受験競争を抑制し、ゆとりある教育へと向かっていました。
それまでの過度な受験戦争に対する批判は、ぼくらの子供の頃(70~80年代)には、ある程度の「風潮」にもなっていたように思います。例えばドラマの金八先生では、学校の落ちこぼれ「腐ったミカン」を切り捨てることを批判していました。ぼくが大好きだったマンガの「ハイスクール奇面組!」は、では、学力や運動神経、ルックスなど、世間一般で競争の対象になりそうなものを持たざる者たち(=奇面組)に焦点を当てたマンガでした。
ただ、こうした70年代~80年代は、「競争は善だ」という考えと「競争は悪だ」という両極端な考えしかなかったようにも思います。そうした二元論に浸り切ったぼくなので、競争社会で行き詰まった時に、真反対の「競争から降りよう」ということを、そんなに躊躇せずに決断できたのかもしれません。
しかし「競争」を過度に否定することは、実は「競争」を肯定していることでもある
しかし今となって思うのは、「競争」を過度に否定することは、実は「競争」を肯定していることでもあると思うんですよね。「競争」にまつわる価値を感じているからこそ、競争を否定したいという気持ちが湧いている、ということですかね。本当に「競争」に価値を見出していなければ、競争を否定するということもないはずです。さらにいうと、ぼくが抱く「競争を否定したい」という気持ちは、当時の二元論的風潮の影響を色濃く受けたものでもあるわけです。
競争を両極端に評価するのではなく、競争と適切な距離感を保ち、ほどほどに付き合っていくことが重要なのではないか、という考え方もあるように今は思っています。競争に過度な価値を覚える必要はないが、「競争なんて全く意味もない」と言えば幸せに生きていけるわけでもありませんからね。
確かにぼくは「もう競争から降りよう」と思った時、それまで競争にとらわれていた自分から解き放たれた開放感もあり、結構な自己満足を覚えていました。しかしそこに安住して、競争からことごとく降りることも、幸せになることからはかけ離れているのかもしれません。これは相対的なものでもありますが、競争社会に行き詰まるくらいのめり込んだからこそ、競争から降りるカタルシスを味わえたのかもしれないのですから。
ぼくの娘氏には、やがて「競争社会」が訪れます。彼女に「競争社会なんてゴミ。脱落したって生きていける」と胸を張って言い切れるのか?という葛藤があったりもします。(かといって競争に勝ち残るようにけしかけるつもりもないですけど)
じゃあ、どうすりゃいいのか?ということについては自分の中で答えは出ていません。これまでのぼくは競争を否定するか肯定するかの両極端で生きてきました。だからいまこうして悩んでいるのは、競争との距離のとり方を真剣に考えてきていなかったツケを払っているのでしょう。
競争と適切な距離感を保ちながら生きていくと文字で書くのは簡単です。でもそういう生き方は、ぼくが死ぬまで探索しつづけないといけないのかもしれません。