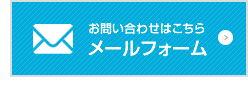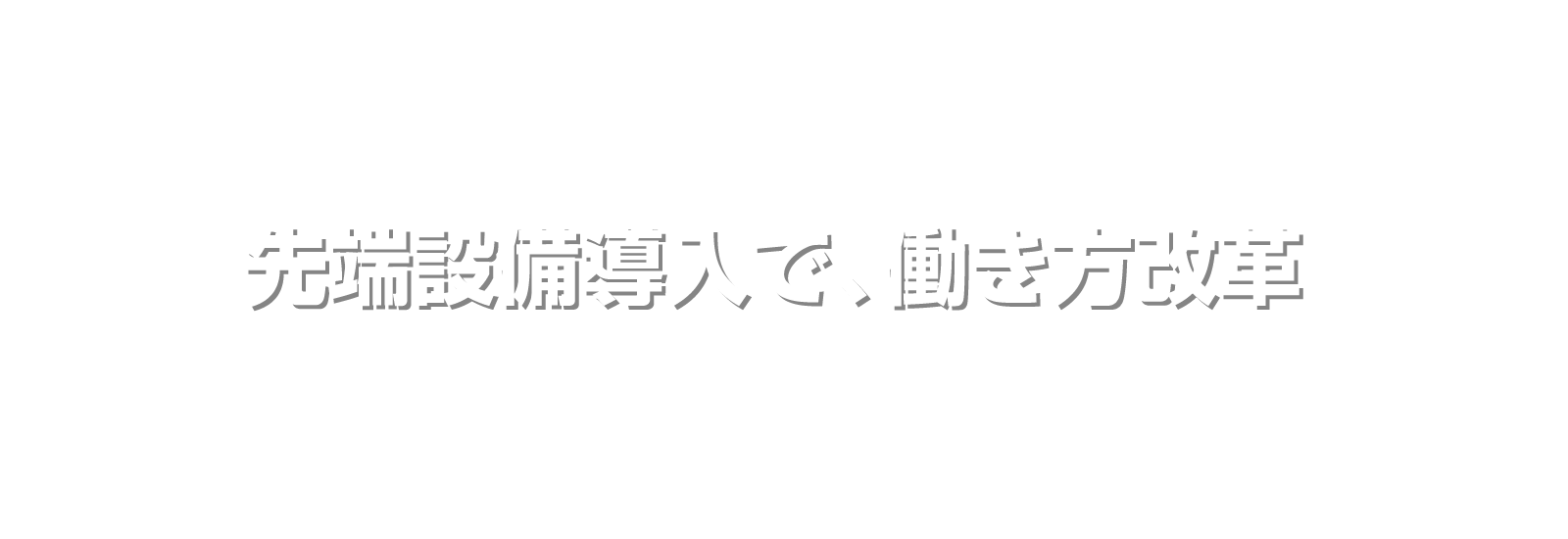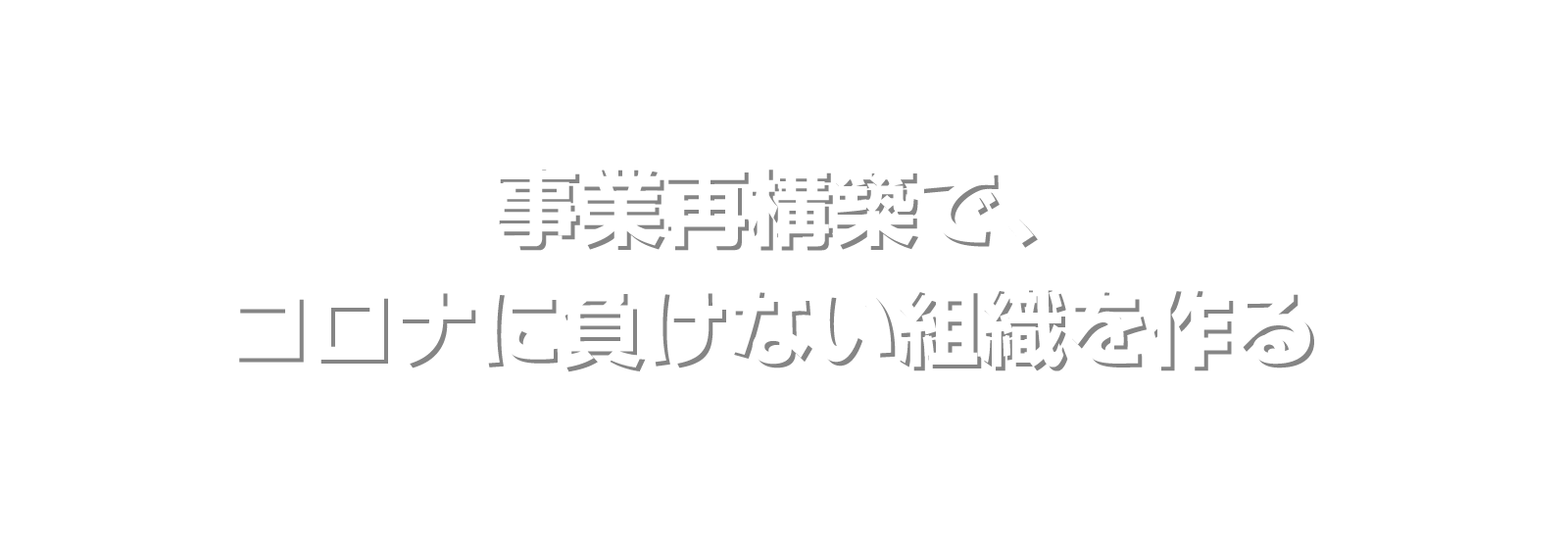おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO42001各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.3「役割・責任・権限」について解説します。
スポンサーリンク
動画でも解説しています(無料・登録不要)
はじめに
AIプロジェクトに限りませんが、会社では「これ、一体誰の仕事?」と混乱したり、責任のなすりつけ合いが起きたりしますよね。こうした事態は、AIプロジェクトを組織として取り組む上でもつまずきの原因になります。
そこで今回は、なぜ役割分担が必要で、具体的に何を決めればよいのかを解説したいと思います。それでは、さっそく見ていきましょう!
箇条5.3「役割・責任・権限」の位置づけ
まず、今日説明する箇条5.3「役割・責任・権限」の位置づけについて解説しましょう。
この箇条は、社長や事業部長といったトップマネジメントに求められる項目の一つです。トップが部長や課長の役割を決め、そして部長や課長が、現場にいる私たち一人ひとりの役割を決める、というのが一般的な役割や責任の決め方ですよね。つまり、私たちの仕事の根っこをたどると、必ずトップに行き着くわけです。だから箇条5.3では、この役割分担の仕組み作りを、「おおもと」であるトップが責任を持って作るよう求めています。
「役割」「責任」「権限」とは
箇条5.3を理解するために、まず「役割」「責任」「権限」という言葉の意味を確認しましょう。

まず「役割」とは、組織の中で期待されている機能や、立場のことを指します。 例えば、代表取締役、AI推進部長、開発課長といった、組織図に書かれているようなポジションがこれにあたります。
次に「責任」です。これはその役割の人が「やるべきこと」です。 トップマネジメントであれば「AI活用の方針を組織全体に伝える」という責任がありますし、管理者であれば「AIシステムのパフォーマンスを監視・測定する」責任、そして現場の担当者であれば「決められた手順通りにAIを運用する」といった責任が考えられます。
そして「権限」とは、その責任を果たすために必要な、「他人に指示をしたり、何かを実行したりする権利」のことです。 部門の目標を設定する権限や、作業方法の変更を承認する権限などがこれにあたります。
なぜ責任・権限を明確にする必要があるのか
そもそもなぜ責任・権限を明確にする必要があるのでしょうか。それが決まっていないと、AIプロジェクトが混乱するからですね。

この図のように、誰に何を聞いたらいいかわからなかったり、責任のなすりつけがおきたり、対応が遅れたりと、最悪の事態に陥ります。この根本原因は、「誰が、何をやるのか」という責任・権限が曖昧だからですよね。「誰かがやってくれるだろう」という思い込みが、リスクを見逃したり、プロジェクトを停滞させてしまうというのは、組織あるあるですよね。こうした事態を防ぐために、責任・権限の明確化が不可欠だということです。
箇条5.3の要求事項
箇条5.3の要求事項は2つあります。一つは役割ごとの責任・権限を決めるということ。もう一つは全体をまとめる「管理者」役を決めるということです。
この2つの要求事項については、次回解説します。