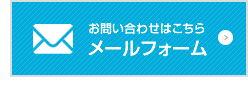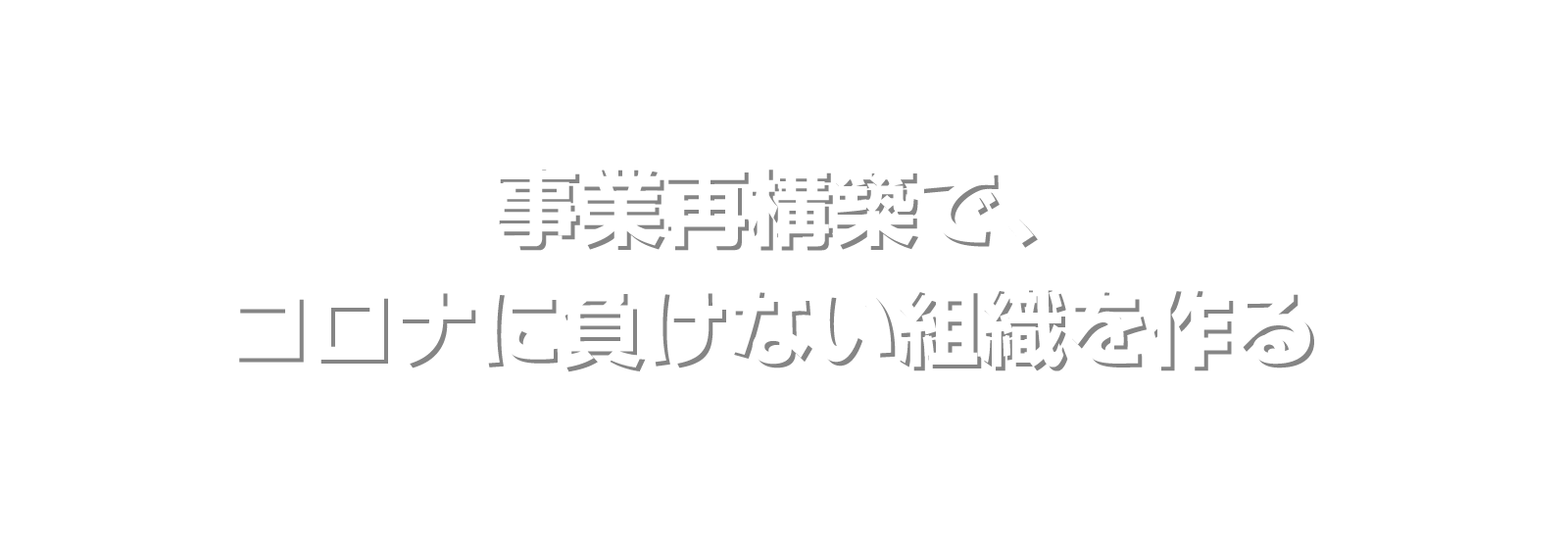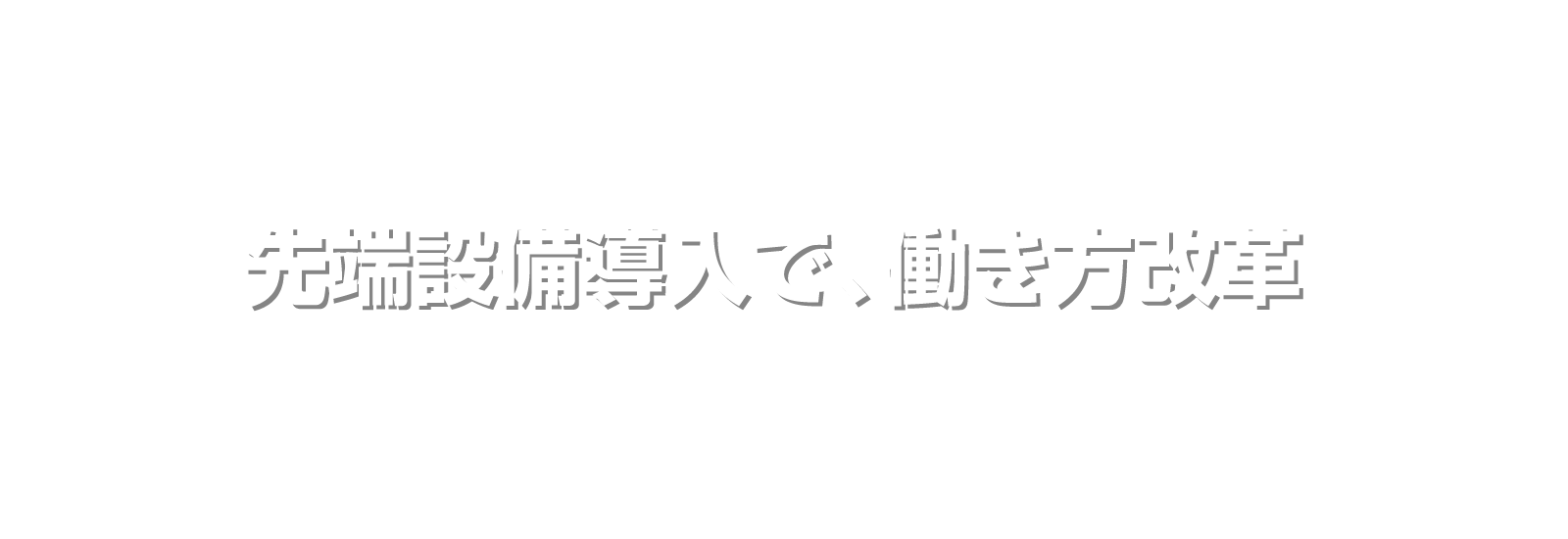おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
6月26日、日経新聞は、経済産業省が、深刻な人手不足に悩む中小企業のロボット導入を支援するため、「専門的な助言者」の育成に乗り出すことを報じました。この記事について解説します。
スポンサーリンク
『中小企業のロボット導入に助言役 補助金審査に加味も検討、経産省』
国が「ロボット導入助言者」の育成に乗り出す背景
経産省がこの施策を主導する背景には、やはり深刻な「人手不足」があると思います。ごソンジの通り、少子高齢化による生産年齢人口の減少は、特に中小企業の現場を直撃していますからね。
そしてもう一つの理由は「市場のミスマッチ」にあると思います。ロボット導入を実際に支援するのはシステムインテグレータ(SIer)ですが、日経の記事でも指摘しているように、彼らはやはり、ビジネスとして利益率の高い大企業の大型案件を優先しがちです。手間がかかり契約額も小さい中小企業の案件は敬遠されている印象がありますね。こうしたシステムインテグレーターの姿勢も、中小企業におけるロボット導入の障壁になっているのでははないかと思います。
経産省は「中小企業省力化投資補助金(一般型)」という、ロボット導入を主たる目的とした補助金施策を行っていますが、カネだけではなくヒトも両輪で支援することで、中小企業の人手不足解消を本格的に加速させようとしているのだと思います。
この施策は本当に機能するのか
この施策は、中小企業のロボット導入を大きく前進させる可能性を秘めていますが、成功への道は平坦ではないと、ぼくは思います。
もちろん、ロボット導入に必要な「ヒト」と「カネ」を経産省が支援をして準備をして、しかも補助金の加点となる仕組みは、ロボット導入を促進する可能性はあります。
ただ、 全国に約300万社以上あるといわれる中小企業をカバーできるだけの頭数と、その全員が高い専門性を維持する質を担保できるかというのは、かなり高いハードルではないかと思います。ちなみに助言者の対象は、製造業のエンジニア経験者などだそうですが、わざわざそうした人材がこの助言者になるインセンティブがあるのかというのは未知数ですね。仮に立ち上げの時点でそれなりの人材が集まったとして、それを長期間にわたり維持できるだけの持続可能性があるかは疑問ですね。
また記事によると、2026年度以降は自治体などが資金を拠出する計画だそうですが、財政的に厳しい自治体がこの施策にお金を出すインセンティブもよくわかりませんね。ロボットが導入されると固定資産税が増えて、あわよくば法人住民税も増えるかもしれない、という程度のインセンティブだと、弱すぎるのではないかという気もします。
多くの課題はありますが、中小企業の現場に寄り添い、変革の第一歩を後押しするのは人間しかいないわけですから、こうした取り組みが製造業の人手不足を解消する一歩となればいいのですが。