おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015 各解説シリーズ、今日は箇条10.1「一般」について解説をします。今回は、 附属書A10.1に示されている「改善」の例も解説します。
もくじ
動画でも解説しています(無料・登録不要)
前回の記事はこちら
附属書A10.1に示される改善の例
ISO14001:2015 附属書A10.1には、改善の例が示されています。
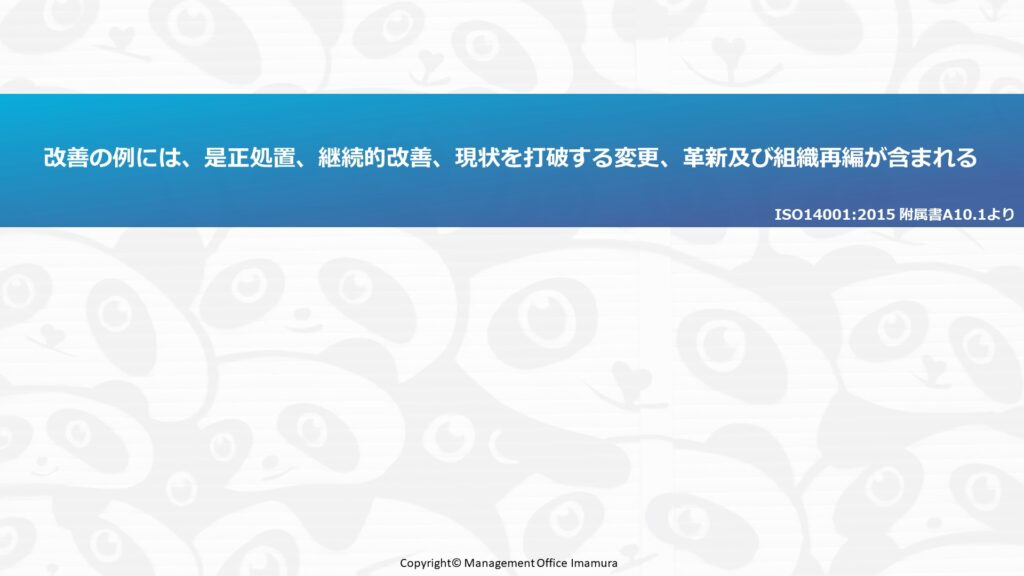
改善というのは、単に起きた不具合に対して修正したり是正したりするだけではなく、もっと他の観点があると言っていますね。
是正処置は、ご存知の通り、起きた不適合に対して再発防止策を取ることですね。
継続的改善とは、地道にコツコツと改善を積み重ねて、徐々に効果(パフォーマンス)をあげていくということです。例えば、プラスチックの使用量をへらすために、歩留まりを地道に改善していく、みたいなことが継続的改善ですね。
次の現状を打破する変更とはなんでしょうか。これは英語の原文ではbreakthrough changeといいます。大躍進や大発見、大きな進歩のことで、障壁となっていたことがらを突破するようなことというニュアンスがあります。これはプラスチック使用量削減の例でいうと、バイオマスプラスチックを使うようにする、みたいなことですかね。
次の「革新」というのがあります。これは英語の原文ではinnovationですね。「経営革新」ともいいますね。これは今までにない製品を作るとか、今までにない生産方法を導入する、みたいなことですね。例えばプラスチック使用量を減らすために、工程をまるっきり見直すとか、AIとかIoTを使う、みたいなイメージでしょうか。
最後の組織再編がどう改善につながるのかっていうのはちょっとよくわかりませんけど、権限を移譲したり、プロジェクトチームとかクロスファンクショナルチームを作ったりするっていうことですかね。組織再編って、改善そのものというよりも、改善を実施するための手段じゃないかって気もしますけどね。
いずれにしても、目の前におきた出来事をなんとかするだけではなく、今までのわが社のあり方ややり方までも含めて見直すことが改善なんですよ、と言っています。こうした深いレベルの改善にも取り組むことが、環境パフォーマンスを高めるために重要なんだということですね。
改善にはトップマネジメントの関与が不可欠
今までのわが社のあり方ややり方までも含めて見直すことが重要という話をしましたが、そうしたレベルの改善をするには、現場だけでは無理ですよね。今までのわが社のあり方ややり方までも含めて見直す権限のある人が、環境マネジメントシステムの運用にかかわらないといけません。
それは誰かというと、やはりトップマネジメントなんでしょうね。トップが不在のマネジメントシステムはうまくいかないということを最後に強調して終わりたいと思います。


